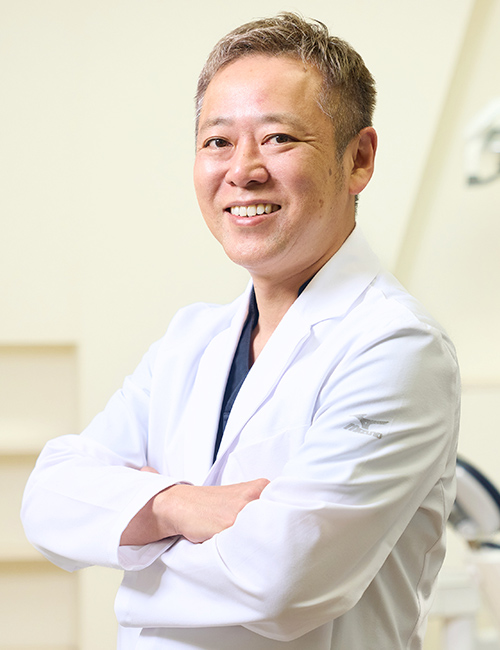マウスピース矯正(透明な取り外し式の矯正装置)は、目立ちにくく通院の手間も抑えられる点で人気がありますが、「どのくらい期間がかかるか」は最も気になるポイントの一つです。
本記事では、マウスピース矯正の期間の目安を、全体矯正・部分矯正それぞれの観点や、ワイヤー矯正との比較を交えながら解説します。また、期間が長くなってしまう原因や、できるだけ短く抑えるコツについても掘り下げます。
矯正を検討中の方が見通しを持てるよう、実際のケースを交えてわかりやすく解説します。
小児矯正を検討中の方は、実績豊富な神戸市板宿駅の「のぶ歯科・歯ならび歯科」にご相談ください>
マウスピース矯正の期間はどれくらい?
全体矯正の場合
マウスピース矯正のうち、歯列全体を整える「全体矯正」に要する期間は、症例の難易度や歯の移動距離、骨の状態、装着時間の遵守度などにより大きく異なります。
多くのクリニックでは、全体矯正において 1年〜2年 を目安とすることが多いです。
重度の不正咬合、抜歯を伴う治療、顎のズレや骨格的な問題がある場合は 2年以上、場合によっては3年近くかかる ケースもあります。
動的矯正(実際に歯を動かす期間)だけで1年半~2年半程度かかることもあり、治療後には 保定期間(リテーナーで後戻りを防ぐ期間) が設けられるため、これも含めると 全体として3~4年程度 に及ぶこともあります。
つまり、全体矯正では「動的矯正期間(1〜2年程度)」+「保定期間(1〜2年程度)」を見込む必要があります。
部分矯正の場合
一方、部分矯正(前歯のすき間・軽度な不正の調整など、限られた範囲)については、比較的短期間で済む可能性があります。
一般的には 1年半程度 が目安とされ、軽度な症例では 6か月〜1年程度 で完了することもあります。
ただし、部分矯正でも「歯の移動距離が大きい」「隣接歯との干渉がある」「歯根の方向を変える必要がある」などの条件があると期間が延びることがあります。
まとめ目安表
| 矯正範囲 | 動的矯正期間の目安 | 保定期間も含めた総期間の可能性 |
| 全体矯正 | 1年2年、重症例は2年以上 | 2年~4年程度(動的+保定含む) |
| 部分矯正 | 1年半、軽症例は6か月〜1年程度 | 1年~2年程度(動的+保定含む) |
このように、マウスピース矯正の期間には比較的大きな幅があり、「患者さんごとの条件」が非常に重要です。
ワイヤー矯正の期間については、こちらの記事でも解説しています。
マウスピース矯正の期間が長くなる原因
マウスピース矯正の治療期間が予定より長引くことは決して珍しくありません。以下では、主な原因とその背景を解説します。
歯並びの乱れが重度である
出っ歯、叢生(ガタガタ)、捻転、咬合異常(開咬、過蓋咬合など)といった症例の難易度が高い場合、歯を動かす距離が大きくなるため、治療途中で必ずと言ってもいいほど追加シュミレーションを行います。
顎の骨格的ズレを伴うケースでは、骨格的矯正を併用する必要が出てくることもあり、これが期間を延ばす要因になります。
また、抜歯を必要とするケースでは、スペースを閉じる期間が追加でかかることがあります。
マウスピースを正しく装着できていない
マウスピース型矯正の大きな弱点は、取り外せるという性質ゆえに装着時間の遵守が患者さんの自己管理に依存しやすいという点です。
一般的に、1日20時間以上装着することが推奨され、これを守らないと歯の移動が計画通りに進まず、次のマウスピースを早めに交換できない、または再スキャンが必要になることがあります。
外している時間が多いと、計画通りには歯が動かず、遅延や再設計が起こることがあります。
治療中に虫歯・歯周病になった
矯正治療中は装置周辺にプラークが溜まりやすく、虫歯・歯周炎のリスクが上がります。万一虫歯・歯周病が発生すると、矯正装置の使用を中断して治療を優先する必要があり、矯正の進行が止まり、期間が延びることがあります。
特に、歯とマウスピースの隙間ができたり、洗浄が不十分な場合はトラブルを引き起こしやすくなります。
定期通院を怠った
マウスピース矯正でも、定期的なチェックとマウスピース交換・調整が必要です。来院を怠ると進捗を見落としたり、交換タイミングを逃したりすることがあります。
通院間隔が空きすぎると、その分治療計画からずれてしまい、延長につながる可能性があります。
歯の動きが遅い・骨の代謝が鈍い
成人矯正では骨の代謝・歯槽骨の再構築が子どもより遅くなる傾向があり、歯の動きが遅くなることがあります。
骨密度、歯根長、歯周組織の状態、年齢、生活習慣(喫煙・偏食など)も歯の動きに影響を与えることがあります。
無理な力をかけず、生理的な範囲で動かすことを優先するクリニックでは、慎重に進める分だけ期間が長くなることもあります。
計画通りに動かない
矯正計画は理論上「この歯をこの方向に動かす」という設計をしますが、実際には隣接歯の干渉や骨の抵抗などによりズレが生じることがあります。
このズレを修正するため、新たなスキャン・マウスピースの再作成が必要となり、その間に治療が一時止まるため、期間が延びます。
患者の習癖の影響
舌癖(舌で歯を押す癖)、頬杖、口呼吸、噛みしめ癖などがあると、矯正した歯を本来の位置に保持しにくく、ずれや後戻り傾向が現れることがあります。
これらを改善しながら進める場合、安定化を重視して慎重に治療が行われるため、期間が長めに設定されます。
装置・素材・設計の制約
マウスピースの材質や設計によって、かけられる力や方向性が制限されます。
また、マウスピース型矯正は1枚で動かせる量が限られており、移動距離が大きい歯では多数枚のマウスピースを順次使う必要があります。これが結果的に期間を長くする要因になります。
歯科医師が歯根吸収などのリスクを考慮し、安全を優先する計画を立てる場合もあります。
マウスピース矯正の期間を短くする方法
マウスピース矯正をできるだけ短期間で終えるためには、以下のポイントを意識することが重要です。
マウスピースの装着ルールを守る

1日20時間以上の装着を確実に守ることが基本です。外すのは食事や歯磨きの時だけにとどめ、脱着の回数を減らすよう心がけましょう。装着時間が足りない日が続くと、計画が狂いやすくなります。
定期的に通院する
通院スケジュールを守り、マウスピースの適合や交換のタイミングをチェックしてもらいましょう。問題があれば早めに調整を行うことで、治療計画をスムーズに進めることができます。
口腔内を清潔に保つ
毎日のブラッシングやフロス、マウスピースの洗浄を徹底し、虫歯や歯周病を予防しましょう。矯正中に虫歯治療が必要になると期間が延びるため、予防が何より大切です。
計画通りに動かないときは早めに修正
マウスピースを装着して不適合を覚えたら、早めに歯科医院に相談しましょう。早期対応でロスを最小限に抑えられます。
習癖の改善
舌癖や頬杖、口呼吸などの悪習癖がある場合は、トレーニングや生活習慣の見直しを行いましょう。口腔筋機能療法(MFT)などを併用することで、後戻りを防ぐ効果も期待できます。
健康的な生活を意識する
バランスの良い食事、十分な睡眠、禁煙を心がけ、骨の代謝を良好に保ちましょう。体の状態が良いほど、歯の移動も順調に進みやすくなります。
マウスピース矯正とワイヤー矯正の期間の違い
一般的には、ワイヤー矯正の方が治療期間がやや短くなる傾向があります。ワイヤー矯正は固定式で自己管理の影響を受けにくく、計画通り進みやすいのが特徴です。
一方、マウスピース矯正は装着時間や通院状況によって期間が変動しやすい反面、軽度の症例では1年以内で完了するケースもあります。
どちらが早いかは症例によりますが、確実に進めたい方はワイヤー矯正、生活に合わせて進めたい方はマウスピース矯正が適しています。
マウスピース矯正のメリット・デメリットについては、こちらの記事をご覧ください。
歯列矯正を検討している方は、神戸市須磨区ののぶ歯科・歯ならび歯科にご相談ください

矯正治療を始めようとしても、「自分の場合はどれくらい期間がかかるのか」「どの方法が合っているか」など、不安を抱える方は少なくありません。
神戸市須磨区にあるのぶ歯科・歯ならび歯科では、こうしたお悩みに丁寧に対応し、個別の治療計画を立てるための相談を随時受け付けています。
当院では、ワイヤー矯正・マウスピース矯正の両方を取り扱っており、患者さまの希望・ライフスタイル・歯並びの状態を踏まえて最適な方法をご提案します。
初回の無料矯正相談会も実施していますので、期間・費用・治療方針について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
美しい歯並びは見た目だけでなく、咀嚼や発音、歯の健康にも関わります。のぶ歯科・歯ならび歯科があなたの理想の笑顔づくりをサポートいたします。